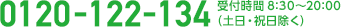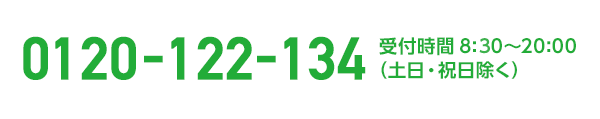寸法測定と予兆管理(1/4)
- 分類:
- 最近話題の寸法測定

トラブルを未然に防ぎ、品質の均一化に効果的な管理方法とは
ものづくりにおける製造工程は、設計品質を確保した製品を継続的に生産する役目を担っています。しかし同じ材料を使い、同じ機械で、同じ人間が、同じ方法でつくったとしても必ず品質にはバラツキが発生します。この品質のバラツキを管理し、一定の水準で安定させるためには品質管理が欠かせません。
さらに近年では、品質管理からさらに一歩踏み込んだ「予兆管理」という考え方が浸透しつつあります。そこで今回は、不良品の発生を未然に防ぐ予兆管理に迫ります。
予兆管理とは
予兆とは「前触れ」や「前兆」のことで、何かしらの変化や事象が起こる前のこと。よく、ナマズが暴れることを地震の予兆と言いますが、何かしらの変化や事象が起こる前には前触れがあるものです。予兆管理では、トラブルや事故などが発生しないように予兆または異常を察知し、迅速に問題点を洗い出し、改善することが基本。そのことから「異常管理」と呼ばれることもあります。
ニュースで自動車の大型リコールなどが取り上げられることがありますよね? このような報道を見るとトラブルが突然起こったように感じますが、本当にそうなのでしょうか? 製造現場レベルで考えたときに本当に品質に異常はなかったのでしょうか? 中には予期せぬトラブルから起きてしまったリコールもあると思いますが、その多くは何かしら改善する余地があったはず。それらを防ぐことも予兆管理のひとつです。
予兆管理に求められること
製造現場では作業担当者が生産・作業日報に記入し、管理者がそれを確認して品質管理を行います。しかし、作業担当者が「異常なし」「問題なし」と記入しても、実はトラブルにつながる小さな変化が発生していたかもしれません。
「工作機械の調子が悪くて調整を行った」「作業中に機械から異音が発生していた」「溶接面の色がいつもと違った」「プレス加工でバリがいつもより多かった」といった変化があったとしても設計品質の範囲内であれば、作業担当者は「異常なし」と報告するでしょう。このような正常と異常の中間と言える変化が予兆です。
これらの小さな変化を管理者が認識し、原因を追及し、改善し、さらに次回以降のトラブルを防止するために標準化することが重要なのです。標準化とは、製造ルールを定めることはもちろん、寸法などの数値で明確にすることも大切。数値であれば明確な判断基準となり、変化にも気づきやすく、素早く確実に改善策を講じることができます。形や大きさだけではなく、色、重さ、硬さなどを数値化し、異常を定義することも予兆管理には欠かせません。
また、これらの異常を正確に記録として残すことも必要。予兆管理では、異常が起こる傾向を知り、予測することも重要です。そこで最初に取り組むべきは、現場担当者から管理者に正確に小さな変化が伝わる仕組みづくりです。