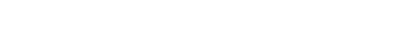曲げ試験
丸棒または角棒状の試験片に曲げようとする力を加え、曲げ荷重・たわみ量・曲げ強さ・曲げ弾性率・破断伸び・耐屈曲回数を測定する試験です。
ここでは、曲げ試験の種類や特徴、材料による測定データの違いなどについて説明します。
試験の対象は、主に金属・プラスチック・セラミックなどです。
試験の方法には、試験片の両端を支えて中央に荷重を加える「3点曲げ」、左右両支点から等しい距離の位置に同じ大きさの2つの荷重を加える「4点曲げ」などの方法があります。
3点曲げは容易な試験方法ですが、試験片に加わる曲げの力が一様ではなく、基本的性質を調べるには不向きといわれます。しかし、材料の曲げ加工のしやすさを調べるような工業的試験は、この方法で行われることが一般的といわれています。評価方法としては、試験片を規定の内側半径を持つ円弧状にまで曲げたとき、湾曲部の外側に生ずる亀裂の有無により材料の曲げ加工のしやすさを判断します。
4点曲げは2つの荷重の間で材料に加わる曲げの力が一様となるため、純粋な曲げの状態になります。曲げに対する材料の基本的性質を調べるのに適しているといわれます。
一般に、脆性材料の場合は「抗折(こうせつ)試験」といわれる曲げ試験で、破壊強度や変形の程度を測定します。また、延性材料の場合は、90度または180度まで屈曲させ、その屈曲性能を試験する「屈曲試験」という曲げ試験で測定します。屈曲負荷を繰り返して破断までの回数を計測する反復屈曲試験や、芯棒に線材を巻き付けて試験片の線材の亀裂性を調べる巻付・巻解試験も曲げ試験の一種といえます。

例:4点曲げ
- 荷重
- 試験体
測定の概要
曲げの荷重や負荷によってひずんだ量、負荷をかけた回数と変形の関係などを計測し記録します。
- 得られるデータ
- 曲げ荷重、たわみ量、曲げ強さ、曲げ弾性率、破断伸び、耐屈曲回数など