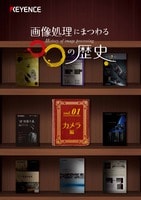- 画像処理を学ぶ
- 理解度チェック
- 画像処理理解度テスト 1
- 画像処理理解度テスト 2
- 画像処理理解度テスト 3
- 画像処理システムの用途
- 業界別導入事例
- 選定のポイント
- 導入のメリット
画像処理にまつわる歴史:照明編
画像処理に必要不可欠なLED照明ですが、開発されるまでに様々な形状や手法を経てきました。
発光の原理から特長を理解することで、さらなる安定検査を実現していただくために、今回は照明の誕生から現在の形に至るまでの歴史をご紹介します。
あかり(照明)の歴史
眩しい太陽光に幻想的な月光。日本人は自然光を、あかり(照明)に利用してきました。
屋外では焚き火や松明、室内は、ろうそくなど人工のあかりを手にし、暗い夜も生活時間になります。
江戸期に発明された短檠(たんけい)は行灯へと発展していきます。
明治時代に入ると、西洋文化のあかりが登場します。石油ランプは、和のあかりとは比較にならない明るさと利便性をもたらします。続いて産業革命とともに実用化されたガス灯が1872年、電灯が1878年に相次いで国内にも出現し、昭和初期まで世を二分する主役争いを展開しました。
あかりの歴史、石油ランプとガス灯

アーク灯から白熱灯へ
「明るさは白昼の如し」と明治の人々を驚かせた初期の電灯は、炭素アーク灯です。
その後、エジソンが白熱灯(カーボン電球)を発明し、さらに黄色い光のカーボン電球よりも小型で、明るく白い光のタングステン電球が登場します。エジソンはカーボン電球のフィラメントに、日本の竹ひごを使いました。一方、タングステン電球には、融点の高い金属フィラメントが使われました。
では、ここで質問を一つ。
「エジソンに負けない、電球の進化に貢献した日本人技術者は?」――。正解は、フィラメントを螺旋状にする二重コイルを発明した三浦順一、光を拡散し和らげるガラスバルブのフロスト加工(内面つや消し)を実現した不破橘三です。二人の手によって、タングステン電球は高い照明効率と光の質に改良され、電灯の普及を後押ししました。
電灯の進化、アーク灯にカーボン電球、タングステン電球

ルミネセンス(蛍光灯)の時代
白熱灯に代わって戦後、あかりの主役の座を奪ったのが蛍光灯です。1938年にアメリカの技師・インマンが開発し、日本では1940年に始まる国宝・法隆寺金堂壁画の模写照明に採用され、認知度が高まりました。戦時中は、潜水艦や防空壕にも使われました。
蛍光灯は、水銀蒸気中の二つの電極で放電して生じる紫外線(不可視光)を、ガラス管の内側に塗った蛍光体で眼に見える光(可視光)に変えることに成功しました。その後、水銀から発光効率の高い金属元素へと改善されますが、発光の基本原理は変わっていません。
熱によるエネルギーロスが小さく、同一電力で白熱灯の3~ 5倍の光量が得られるため、「省エネで、白く明るい」蛍光灯は、1960年代から急速に普及します。
石油ランプやガス灯、白熱電球は発熱による発光(放射熱)でしたが、蛍光灯は放電による蛍光現象(ルミネセンス)です。こうして、ルミネセンス時代が到来しました。
初期の蛍光灯としくみ、発光方法の違い

「量」から「質」の時代へ
戦後の復興を象徴するあかりとして「量」を満たした蛍光灯は、「質」の時代へと突入します。
棒状の直管型や円形の環型に加えて、発光効率と演色性(色のきれいな見え方)を両立させた三波長域発光型、コンパクトで低消費電力の電球型などが開発されました。
質の高いあかりの追求は、蛍光灯一辺倒ではありません。蛍光灯の数十倍の光の量があるHIDランプ(高輝度放電ランプ)は街頭や道路、ビル、野球場など屋外照明に利用されています。
人工の光で最も太陽光に近いと言われる白熱灯も、食欲を増進させる暖色の演出効果や落ち着いた空間演出に優れ、高効率、長寿命のハロゲン電球やクリプトン電球が登場しています。
質の高い光のいろいろ(蛍光灯・HID ランプ・白熱灯)

LED(発光ダイオード)が登場
白熱灯や蛍光灯に比べ、省エネ効果の高い照明がLED(Light Emitting Diode・発光ダイオード)です。
P(ポジティブ)型とN(ネガティブ)型、2種類の半導体を接合したLEDに電流を流して発光するしくみです。赤や緑のLEDは1960年代から実用化されましたが、1993年に高輝度青色LED、続いて96年に白色LEDが開発され、多用途の実用化が進みました。
LEDは砲弾型とチップ型があります。砲弾型は直進して発光し、真正面から見ると明るく、チップ型は横に広く拡散して発光します。
砲弾型は信号機に、チップ型はケータイの液晶画面用バックライトなどに利用され、中間で直進性と拡散性のバランスが良いフラット型もあります。
消費電力が小さく約4万時間の長寿命でCO2排出を低減し、発光素子が米粒ほどで小型・軽量化にも適しています。紫外線や赤外線をほとんど出さないため美術品や食品にもやさしく、最近では一般家庭や街路などにも普及してきています。
LEDのしくみと特徴、砲弾型とチップの型

有機ELのしくみ、照明の単位と選択肢

あかりの未来形、LED×EL×自然光
あかりの未来を切り拓くのは、LEDだけではありません。有機EL(Organic Electro Luminescence)は、「点」のLEDに対してシート状の「面」光源です。
軽くて薄く曲げることも可能で、電子ペーパーなどディスプレイ分野への用途開発が進み、将来は発光する壁や天井の開発も期待されています。
あかりの原点である自然光を効果的に利用する採光システムも進化しています。生体リズムや殺菌効果など快適な照明空間を創出し、究極のクリーンエネルギーとしても見直されています。
LEDや有機EL、レーザー光など最先端の「フォトニクス・テクノロジー」(光と科学の応用技術)との相乗効果にも、関心が高まっています。
有機ELのしくみ、照明の単位と選択肢