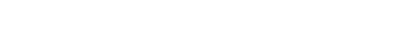はんだ付け
ろう接の中でも、低融点のろう材を使用する「はんだ付け」。ろう付けで用いたレーザーの代わりに、はんだ付けでは光ビームを熱源に使用します。微細接合で活躍する溶接法を紹介します。
はんだごてに代表される、電気による発熱を利用した「はんだ付け」が一般的です。
他に、溶けた「はんだ」に接合する部分を浸して接合する「ディップはんだ付け」や「リフローはんだ付け」があります。
しかし近年、FA(ファクトリオートメーション)における電子部品などの生産では、「光ビームはんだ付け」などが採用されています。
大きな出力の光源から発生する光を反射鏡で集光し、溶接部に焦点を結ばせ、その光エネルギーではんだ付けします。融点の低いはんだ(軟ろう)を用い、ロボットによるピンポイントな接合が可能であるため、高熱に弱い電子部品などの組立の自動化・量産に有効です。
はんだ付けの技術は、処理工法によって大きく3つに分類されます。
こてはんだ付け
ニクロムヒーターなどで熱した「こて」で「はんだ」を溶かし、母材どうしを接合します。こてはヒーターの構造から「ニクロムヒータータイプ」「セラミックヒータータイプ」の2種類に分かれます。
ニクロムヒータータイプは熱容量があるため、金属の接合などに適しています。セラミックヒータータイプはタングステンで作ったヒーターをセラミックで包んで、こて先を内側から加熱します。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適しています。
ディップはんだ付け
溶けた「はんだ」にはんだ付けする部分を浸して接合します。
ディップはんだ付けでは、「はんだ浴」の温度管理と「はんだ槽」の中の不純物の濃度管理が重要です。
リフローはんだ付け
主にプリント基板へのSMD(表面実装部品)の実装に用います。プリント基板の接合部位(ランド)にはんだペーストを印刷し、その上に電子部品をマウントしてからリフロー炉に送り、赤外線や熱風などではんだを溶かして接合します。
熱源には炉中で熱風を用いる方法や赤外線を用いる方法があります。また、電気抵抗やレーザーを熱源とする方法もあります。