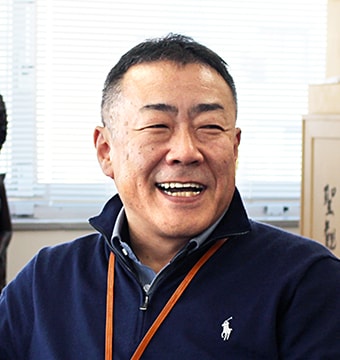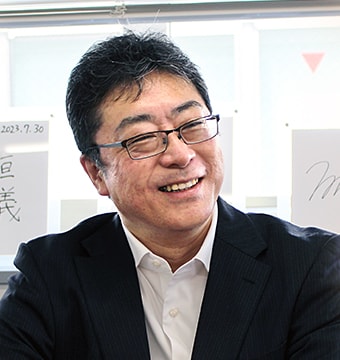現場の意識は相当に変わりました。営業会議では、「今月、今週、これだけ差があります」という説明が、わざわざ求めなくても最初から来るようになりました。
以前は担当者の説明を聞くとき、自分の知りたいことを知るために、次にどこを尋ねるべきか、特にどの部分に強弱をつけ、注意を払うべきかを事前に準備しておく必要がありました。しかし今はKIの画面上に知りたいことが、最初からすべてあります。事前に経営層側でも確認や把握ができるため、話が早いです。
それでも不明なことはマトリックスや要因ツリーでさらに深掘りすればよいし、そもそも「不明な点が特定される」、それ自体が大きな進歩です。
会議では常に「なぜ?」が尋ねられます。報告者はそれに答えるために準備しなければいけない。つまり普段から顧客と会話していないといけないということです。従来は看過、後回ししていたところを、今は事前に動く必要があります。
過去、コロナ禍の影響で、顧客と積極的に対面コミュニケーションをとるのが容易でなくなりました。加えて、当然ながら競合他社も企業努力をしているわけです。
ところが以前は、営業担当者は、自分が意識的に頑張っていることに目がいきがちで、水面下で起きている競合他社と顧客との接点など、不都合なことに意識が向いていませんでした。
意識がないから、顧客に変化の兆しがあっても「なにかあったのですか?」と聞かない。こうなると、競合他社と顧客との接点といった、潜在的なリスクに気が付かない、という懸念がありました。
しかし今は数字の減り方に違和感があるとき、あるいは急に注文が途絶えたりしたとき、KIの分析結果を通じ、1週間、遅くとも1か月以内には気づくことができます。
営業はタイミングが重要で、1年後に気づいて「何があったのでしょうか」と聞いても「今頃、何しに来たの?」となる。だからこそタイムリーに違和感に気づく必要があります。理想的なケースでは、顧客から「よく見ていた」と評価され、チャンスに変わることもあり得ます。問題が起こった1日後とか、それくらいテンポ良ければ、お客様との関係が修復できることも、あったりするんですよね。
顧客側の「変化」はどうしても起きるもので、それに一喜一憂しても仕方がない。そのとき営業担当者のやるべきことは、変化を受け止め、それを早く社内に伝え、場合によっては上司に出動してもらったりすることです。繰り返しになりますが、主観や思い込みをできるだけ排除し、いかにデータを使って客観的に、合理的に変化を捉え、判断に繋げられるか、ここが最も重要な点であると考えています。KIを通じて、こういった意識の変化や風土が、徐々に醸成され拡がっていると、感じています。